NANZAN SYMPHONIC BAND
![]()
Profile
![]()
NSBに関する疑問をここで一気に解決しよう!
NSBパートリスト
| 楽器紹介 | |
|---|---|
| 金管楽器 | 木管楽器&パーカッション |
| トランペット | クラリネット |
| トロンボーン | フルート&オーボエ&ピッコロ |
| ホルン | サクソフォーン |
| ユーフォニウム&チューバ&弦バス | パーカッション |
 楽器紹介
楽器紹介

トランペット
■楽器紹介■
これぞ金管楽器の代表!輝きのある明るい音色で、音楽を華やかに彩る。
リズミカルな音の動きから高らかに響くファンファーレまで、幅広い表現力をもっているから、
クラシック、ジャズ、ポップスなど、いろいろなジャンルからひっぱりだこな楽器。
■歴史■
「トランペット」という名前は、貝殻の一種をあらわすギリシア語から来ているという説があります。
すでに古代文明の時代には、青銅や銀を使ったラッパが作られていました。古代エジプトの壁画にも、
トランペットを吹く人の姿(あくまで横向きです、しかも片手で吹いてます。さすがエジプト!)が残されています。
紀元前14世紀のツタンカーメン王の墓からは、青銅や銀で作られたトランペットが見つかっています。
材料:真鍮 大きさ:約50cm(管の長さ約140cm)
音域:約2オクターブ半
仲間:コルネット、ピッコロトランペット、C管トランペット、
フリューゲルホルン、ビューグル

トロンボーン
■楽器紹介■
スライドで滑らかに音程を変えることができるので、それを生かした特徴ある演奏をすることができます。
音色は男の人の声に最も近いと言われていて(そうなのか!?)且つ、表現力がとても豊か。
オーケストラや吹奏楽、ジャズやポップスなど色々な面で活躍しています。
■歴史■
トロンボーンの祖先は、ホルンやトランペットと同じく、角笛やほら貝。
11世紀頃に、イスラムの方から、真っ直ぐなトランペット「ナフィール」がヨーロッパに伝わりました。
それがS字(言われて見ればS字かも・・)の形に曲げられるようになったのが、トロンボーンの先がけではないかともいわれています。
15世紀の始めには、最初のトロンボーンともいうべき「サクバット」という楽器がヨーロッパに現れています。
ルネサンスの時代にはスライドつきのトランペットが作られました。マウスピースのさしこみの部分をスライドにして
楽器本体を動かすものや、管のU字型に曲がった部分をスライドにしたものなどがあったそうです。
しかしそれらは、まだまだ演奏するのが難しいものだったようです。。
材料:真鍮 大きさ:約120cm(テナー)管の長さ:約270cm
音域:約2オクターブ半(テナー)
仲間:アルトトロンボーン、テナートロンボーン、バストロンボーンなど

ホルン
■楽器紹介■
管が丸く巻かれた面白い形(とりあえず「カタツムリみたいな」というと一般人にも何故か通じる)をしています。
音色は柔らかく、他の楽器の音とよくとけあう。
■歴史■
ホルンの祖先はほら貝や、ヒツジや牛の角でできた角笛です。遠くまでよく響くので合図を送るのに使われていました。
お祭りなどでも使われていたようです。スイスでは今でも「アンペルホルン」と呼ばれる昔ながらのホルンが親しまれています。
今から約2000年前のローマの軍隊では、青銅の管を丸く曲げた「コルヌ」と呼ばれる角笛が使われていました。
戦いや競技の時には欠かせない楽器だったようです。
材料:真鍮 大きさ:約40cm 管の長さ:約280〜360cm
音域:約4オクターブ(金管楽器の中では最高)
仲間:アンペルホルン メロフォン ワーグナーチューバ

ユーチュー弦
(ふざけていると思われるのはイヤなので一応弁明しますが、ユーフォとチューバと弦バスのことですよ)
ユーフォニウム
■楽器紹介■柔らかな音色を出せる楕円形の形をした楽器。ホルンよりも音域が低いそうです。 マウスピースがトロンボーンと同一のことから、この2パート間で移動があっても楽器の音が出しやすいといった利点があります。
材料:真鍮
チューバ
■楽器紹介■金管楽器の中で最も低い音域を受け持つ楽器。ふくよかで豊かな音色でハーモニーをしっかりと支える役割を持っています。
■歴史■
チューバの祖先についてはいろいろな説がありますが、ヘビのような形(!)をした「セルパン」ではないかといわれています。 木の内側をくりぬいて皮を張り、音程を変えるための穴をあけて作られた、低い音域の楽器です。 16世紀ごろ、イタリアやフランスの教会で歌の伴奏に使われていました。 しかし、正しい音程で吹くのがむずかしかったので、しだいに使われなくなっていきました(そ、そんな・・・)。 チューバが作られる前までは、低い音が出る金属製の楽器「オフィクレイド」がオーケストラで活躍していました。 音程を変えられるバルブがまだ発明されていなかったので、ファゴットのようにキーをおさえて音程を変えていました。
材料:真鍮 大きさ:約80cm(B♭管) 管の長さ:約5.5m
音域:約2オクターブ半
仲間:スーザフォンなど
弦バス
■楽器紹介■コントラバスのこと。バイオリンの中で一番大きくて「ダブルベース」と呼ばれることもあります。 形にも特徴があって、バイオリンと比べると撫肩(ああ・・なるほど)で大きいけれど弓の長さは一番短いものになっています。 チューバと同じく最も低い音域を扱っています。
■歴史■
コントラバスの祖先は、バイオリンなどと同じく狩に使われた弓だといわれています。 指ではじいてびゅんびゅん(!?)と鳴らしたり、棒などで軽くたたいて(!)音を出したりしていたようです。 コントラバスの原型は、中世から17世紀ごろまで使われていたビオールという弦楽器のなかの低い音域を受け持つ ビオローネという楽器だったといわれています。ビオローネという楽器は、16世紀ごろ、やや高い音域の音を出すチェロと 低い音を出すコントラバスとに分かれました。ビオローネにあったフレットも、しだいになくなりました。 しかし、17世紀から18世紀にかけては、弦の数や、楽器の細部の形、それぞれの弦の音の高さも、時代や国によってさまざまでした。
材料:木、スチール弦、ガット弦、ガットの胴巻きまたは鋼巻き弦(弓には馬の尾の毛を使っているそうです)
大きさ:約180cm
音域:約2オクターブ+α
仲間:バイオリン、ビオラ、チェロなど
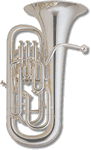


クラリネット
■楽器紹介■
温かで明るい音からちょっと不気味(!)な怖い音まで色々な表情が出せる楽器。強弱も自由自在で幅広いジャンルで活躍中。
■歴史■
大昔から笛はお祭りや合図などで広く使われていました。クラリネットは「シャリュモー」(愉快な名前・・)という木でできた
縦笛がもとになったと言われています。18世紀の始めのころ、ドイツのデンナーという楽器作りの名人が
シャリュモーを改良して2つのキーをつけたリコーダーのような楽器を発明しました。
これがクラリネットであり、名前は「小さなクラリーノ」(クラリーノって・・・)という意味で、更に元を辿ると、
音が明るいことからきていると言われています。
材料:木(アフリカ産黒檀が代表的)、リードはイネ科の植物(暖竹)の茎を削ったもの
大きさ:約70cm
仲間:アルトクラリネット、A管クラリネット、E♭管クラリネット、バスクラリネットなど

フルート・ピッコロ・オーボエ
フルート
■楽器紹介■金属でできているのに木管楽器パート1。鳥のさえずりのように軽やかで透き通った音が特徴で、 速い音の動きもなめらかな音の動きも両方得意。ソロの演奏でも大合奏でも活躍します。
■歴史■
今ではフルートといえば、横笛の代表選手ですが、昔は縦笛も横笛もどちらも「フルート」と呼ばれていました。 17〜18世紀中ごろまでは、フルートといえば縦笛をさすことが多かったようです。 初め、横笛は管に穴を開けただけの簡単なつくりで、かなり大昔から世界中で使われていたようです。 紀元前2世紀頃のエトルリアの遺跡から掘り出された器の浮き彫りにも横笛を吹く人の姿が見られます。 穴が開いているだけの横笛にキーがひとつつけられたのは17世紀の終わりごろです。 18世紀の始めになるとフルートの教科書も作られ、フルートはお金持ちの人々の間で大流行しました。 プロイセンの王フリードリヒ2世は毎日のように宮殿で音楽会を開き、フルートを吹いていたそうです。
材料:金属(真鍮、金、銀)あるいは黒檀などの木
大きさ:約65cm 直径:約2.5cm
音域:約3オクターブ
仲間:ピッコロ、アルトフルート、バスフルート
ピッコロ
■楽器紹介■「ピッコロ」というのはイタリア語で「小さい」という意味。 管楽器の中でも一番高い音が出るのでオーケストラや吹奏楽の中でもとても目立つ存在。 ここぞという時にキラキラしたするどい音を響かせます。フルートと同じように早い動きの音を演奏するのが得意。
■歴史■
なんだかフルートと同じようなものなので省略。 材料:金属または木製 大きさ:約34cm 音域:約3オクターブ
オーボエ
■楽器紹介■ダブルリード楽器。オーケストラにおいては基準の音。悲しげな美しい音色から明るい音も出せる幅広い表現力を持っている。 ■歴史■
大昔、人々は草の茎を咥え、おしつぶして音を出して楽しんでいました。 そしてだんだん竹や葦のリードをつけた縦笛が作られるようになっていきました。 このような笛の歴史は遠く紀元前から始まっているようです。 古代ギリシャの壁画には、「アウロス」と呼ばれる、葦でできたリードつきの笛を吹く人が描かれています。 リードつきの笛はヨーロッパだけでなく中国や日本にも広がっていきました。


![]()
サックス木低
■楽器紹介■
金属でできているのに木管楽器パート2(それは故にリードのおかげ。・・・フルートは?)。
木管楽器の柔らかな音と金管楽器のような輝きのある音の両方をミックスしたような音色でその音は人の声に似ているとも言われています
(ボーンと同じじゃん・・・)。オーケストラや吹奏楽ではもちろん、ジャズでは主役として大活躍します。
ちなみに本来は(?)、その美しい形状に魅了された新入団員(未経験者)の人気が殺到する楽器でもあります。
■歴史■
サクソフォーンは1840年頃、ベルギー人のアドルフ・サックスがパリで発明したものです。
そのころ合奏の中で木管楽器と金管楽器の音がひとつに溶け合っていなかったので、「木管と金管の橋渡しをするような
楽器を作ろう」と考えたのです。サックスは本体は金属に、形は下のほうが広がる円錐型にしました。
そこへクラリネットのマウスピースとリードを取り付けたのです。こうして生まれたサクソフォーンは金管楽器と木管楽器の
中間のような音色でどちらともよく溶け合いました。「サクソフォーン」という名前は生みの親「サックス」にちなんでつけられています
(でも現在、ほとんど愛称はそのまんまサックスになってしまっているけれど・・・)
材料:真鍮
大きさ:約70cm(アルトサックス)
音域:約2オクターブ半(アルトサックス)←ビオラのような音域
仲間:アルトサックス、テナーサックス、バリトンサックス、バスサックス、ソプラノサックス、ソプラニーノサックスなど

パーカッション
ドラムセット
■楽器紹介■吹奏楽の他にも主にジャズやロック、ポップスなどで活躍!両手両足を使って一人で演奏する。 手2本、足2本で足りるというのが摩訶不思議。
■歴史■
打楽器は人間が最初に手にした楽器だと言われるくらい歴史が古く、長い年月をかけて発達してきました。 ドラムセットは20世紀になって使われるようになりましたが、最初のころはシンバルをバチで叩いて音を出すようにしたもの、 足で叩けるように大太鼓にペダルを取り付けたもの、台に乗せたスネアドラム、木を刳り貫いて音が響くようにしたウッドブロックなど ごく簡単なものでした。1920年代に入ると、ジャズがとてもさかんになり、ドラムセットに使われる楽器やその演奏の仕方も発達しました。 2枚1組のシンバルをペダルを踏むことによって鳴らす「ハイハット・シンバル」や、スネアドラムやシンバルを シャラシャラという音で鳴らす「ワイヤーブラシ」などが考え出されました。また、スネアドラムのヘッドの部分とふちの部分を 同時に叩く「リムショット」という演奏の仕方も生まれました。
材料:木、羽、銅、アルミニウム、皮、またはプラスチック(太鼓の皮)など
ティンパニ
■楽器紹介■マレットで叩いて音を出す打楽器。自由に音程を変えられるのが特徴で、2台〜5台くらいあります。 迫力のあるよく響く音が出るので、合奏の場面では勿論、ソロでも活躍します。
■歴史■
ティンパニの祖先はアラビアの「ナッカーラ」という太鼓です。ナッカーラはお椀の形をした木に皮を張っただけの簡単な太鼓で、2つで1組。 小さなものは腰につけたり首から吊るしたりして、大きなものは馬やラクダの背中に括り付けて演奏しました。 ナッカーラは始め、アラビアやトルコ、エジプトなどを中心に広まっていきましたが、13世紀頃になるとヨーロッパにも伝わりました。 小さなものはネーカーと呼ばれ、14〜15世紀になると軍隊や宮廷の競技で使われたり、踊りや歌の伴奏のリズムを取るためにも使われました。 材料:胴体・・・銅や繊維
ガラスヘッド・・・プラスチックまたは子牛の皮
大きさ:48〜81cmで音程によって様々。
音域:約1オクターブ
マリンバ
■楽器紹介■音程のある打楽器の一つで、木琴の仲間。シロフォンと比べると音板が薄くて音色が柔らかく、音域も低い。 木ならではのまろやかに響く音と、豊かな低音が特徴。
■歴史■
マリンバの祖先ははっきりしませんが、地面に掘った穴に木の板を渡して叩いたのが始まりのようです。 南アフリカのズールー族という人々の間には、マリンバという名の女神が木の板の裏にひょうたんをつけて木琴を作ったという伝説があります。 それでマリンバという名前になったとも言われています。 材料:木、金属 大きさ:約70cm
音域:約4オクターブ
仲間:シロフォン、ビブラフォン、グロッケンなど
その他パーカッションの楽器たち
BD、スネアドラム、シンバル、トライアングル、タンバリン、ボンゴ、コンガ、カスタネット、ウッドブロック、ギロ、 カウベル、ドラ、クラベス、ティンバレス、アゴゴベル、マラカス、ピアニカ(?)等


powerd by 素材屋 マイナ水素 / 音楽fanドットコム(instrument picture), css by pondt