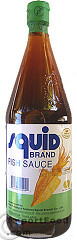2007年7月の雑記
≪7月2日≫
杁中(いりなか)の丸八寿司で昨日、フォルクローレの生演奏があった。
フォルクローレとは、アンデス山地など南米のスペイン語系の民俗音楽である。
ケーナ、サンポーニャ、チャランゴ、ボンボといった独特の味わいのある民俗楽器を用いる。
演奏は名古屋大学フォルクローレ同好会のみなさん。
大学生とは言え、演奏は本格的。卓越した腕前を披露してくれた。
リクエストに応えつつ10曲ほど演奏してくれたが、演奏はすべて暗譜。
何曲くらいレパートリーがあるのか聞いてみたら、
常に40曲くらいはすぐに演奏できる状態にあるという。
この演奏会はお店の開店時間前に、常連客のために催された特別企画。
純日本風のお寿司屋さんなので、こういう企画は珍しいが、
お店の学生アルバイトの一人がケーナの名手で、
この同好会のメンバーなのである。
見事な、そしてとても楽しい演奏会でした。
また聴かせてください。
≪7月3日≫
私のいきつけのお店である居酒屋えっちゃんが
創業10周年を迎えられた。
おめでとうございます。
えっちゃんは一般の家庭のお母さんがお家で作ってくれるような、
ほのぼのとした、おいしい家庭料理のお店である。
おかみさんの気さくで明るくさっぱりとしたお人柄は多くの人に慕われ、
社会人だけでなく、南山大学や名古屋大学などの学生のみなさんにも、
心安らぐ憩いの場として人気がある。
10周年を記念して、新しい緑色の暖簾(のれん)がかけられた。
これは常連客がお金を出し合って作られたものである。
お店の中にも常連の皆さんからのお祝いのお花がたくさん飾られている。
どうぞこれからもよろしくお願いいたします。
えっちゃんにまだ入ったことのない方は、ぜひどうぞ。
(南山の北門から川原通りの方向へ徒歩15分弱です→地図)
≪7月9日≫
週末の土日に、キリスト教学科の一年次生のゼミ合宿が、
岐阜県多治見(たじみ)市にある神言会修道院で行われた。
これが多治見修道院。1930年に建てられたバロック様式の建築。
日本三大修道院のひとつとして知られ、観光名所にもなっている。
また、広いブドウ畑があり、自家製のワインが造られている。
合宿で泊まったのは、修道院本館の裏にあるログハウスである。
しゃれたログハウス(研修センターとも言う)が3棟建てられている。
今回の合宿は、キリスト教学基礎演習の学外授業も兼ねており、
修道院の美しい聖堂の中で、修道院の概要や歴史などについて、
また建築美術史における多治見修道院の位置などについての授業が行われた。
授業の様子も写真に撮りたかったのだが、残念ながら聖堂内は撮影禁止。
ここに聖堂内部の写真と解説が載っていますので、どうぞご覧ください。
↓
<多治見修道院>
授業の後は、修道院の地下にあるワイン醸造所を見学させていただいた。
私も神学生の頃、ここでワイン造りのお手伝いをしたことがある。
建物は地下の部分も昔のまま。いろいろな思い出がある懐かしい場所だ。
勉強会が終わって、夕食のバーベキュー・パーティーの準備。
女子はご飯やサラダを作り、男子は炭火をおこし、肉を焼く。
春のオリエンテーション合宿でもやったので、バーベキューはお手のものである。
緑がいっぱいのブドウ園に、女子たちがシャボン玉を飛ばしていた。
風情あるなあ。(用意がいいなあ)
食事の準備が整い、今回の団長である西脇先生の音頭で乾杯。
とても和やかで楽しい夕食会でした。
バーベキューの後は、ログハウスの中でおしゃべり。
お泊りなので、時間を気にせずのんびりできた。
梅雨時にも関わらず、天候にもめぐまれました。神さまに感謝。
充実した内容の、有意義でとても楽しい合宿でした。
皆さんどうもありがとう。先生方もどうもありがとうございました。
≪7月14日≫
明日、15日は南山大学のオープンキャンパスの予定だったが、
台風4号接近のため、8月に延期になってしまった。(詳しくは→ここ)。
南山のオープンキャンパスは、17年前、
当時副学長だったマルクス先生が提唱されて始まったそうである。
マルクス先生が学長である最後の年となる今年は、
5,000人を超える方々のご来場が予測されている。
8月の開催に、どうぞご期待ください。
さて、話は変わるが、昨日は、私のゼミ(キリスト教学演習)の
三年生メンバーによる研究発表会があった。
これはその後の懇親会。
私のゼミは西洋中世の哲学思想の研究が基本なのだが、
今年の三年生メンバーの研究テーマは、けっこう多彩であった。
トマスにおける知性的実体間の照明
生命の木と十字架
中世の彩飾写本
修道院とビールの発展
テーマが違えば違うほど、内容を互いに理解し合うことが難しくなるが、
それぞれの研究発表はたいへん面白かった。皆さん、どうもご苦労さま。
≪7月19日≫
南山大学は今週で春学期の授業が終了する。
来週から約2週間、学期末試験があり、それが終われば夏休みだ。
私が担当している「ラテン語文法・講読」という授業では、
いろいろなラテン語文学の原典解読にチャレンジしてもらっているが、
今回は初めて、カトーの著作『農業論』(De agri cultura)に挑戦してみた。
まるで日本人(加藤さん)みたいな名前だが、
カトー(Marcus Cato)は古代ローマの有名な政治家のひとりである。
彼は農場も持っていて、『農業論』には、農場の運営に関する事や、
食材の取り扱い、調理法などが書かれている。
さまざまな驚きの新知識を得ることができて、とても興味深かった。
まず、カトーさんが、ものすごいキャベツ大好き人間であることを知った。
もう何というか、手放しの礼讃ぶりなのである。
キャベツはあらゆる野菜に勝り、これほど健康によいものはないと言う。(156-157)
わけても、その消化作用はすばらしく、
生の葉を酢漬けにしたものを食前・食後に食べると、
あたかもまだ何も食事をしていないかのようになるらしい。
それで、好きなだけ暴飲暴食ができるそうである(本当かなあ)。
特に驚いたもののひとつは、ギリシア風ワインの作り方である。
なんと、海水を混ぜ合わせるのだそうだ。次のように記されている。
ギリシア風ワインは次のようにして作るべし。
よく熟したアピキウス種のブドウの実を、よく選んで集める。
その搾り汁1クーレウスに、2クアドランタルの古い海水、
もしくは1モディウスの塩を加えて、ブドウ液を作る。
もしヘルウォルス・ワインを作るなら、琥珀色のワインと
アピキウス・ワインを半々に混ぜて、そこにこのブドウ液を1/30加える。
どんなワインであれ、それにこのブドウ液1/30を加えれば、
ギリシア風ワインのできあがり。(24)
1クーレウスは約522リットル。液体用の皮袋の容量だった。
1クアドランタルは約26リットル。1モディウスは約6.8キログラムである。
海水を混ぜて、本当に美味しいのかなあ。
しかも、「古い海水」とは。(ますます美味しくなさそうだ)
実は別の箇所に、海水(アクア・マリーナ)の仕込み方が記されている。
それによると・・・
海水の仕込み方。
淡水の届かぬ深い海から、1クアドランタルの海水を取ってくる。
1.5リーブラの塩を、煎ってから、棒でかき回しながら加える。
ゆで卵が浮き上がるようになるまで加えたら、止める。
アミンニウス・ワインか普通の白ワインを、2コンギウス注ぎ入れる。
しっかりとかき混ぜて、ピッチが塗られた瓶に入れ、密閉する。(106)
1リーブラは1ポンドと同じである。古代ローマの1ポンドは326グラム。
1コンギウスは約3.2リットル。ピッチ(瀝青、ピクス)は防水などのために塗られた。
この場合、海水とは、むろん地中海の水であろう。
「古い海水」とは、こうやって仕込まれた海水を
長期間おいて寝かせたものなのかも知れない。
それにしても、ゆで卵が浮き上がるほどの塩分・・・
まるで死海の水みたいではないか。
ギリシア風ワインとは、ずいぶん塩辛いものだったのだなあ。
・・・・・。
ご興味のある方、試してみますか?
まず地中海まで行って沖に出て(あるいは深くもぐって)、
26リットルの水を汲んでくる必要がありますが。
≪7月28日≫
現在試験期間中で、これといったネタもないので、
もうひとつ古代ローマの料理のお話でも。
イエス・キリストがパレスティナで活躍した頃のローマの有名な美食家、
アピキウス(Apicius)の著作とされる『料理帳』(De re coquinaria)という文書がある。
これは料理のレシピ集のようなもので、当時の食材や調理法を知るための
貴重な資料となっている。
さて、この著作には、リクアメン(liquamen)という液体の調味料が頻繁に登場する。
このリクアメンがいったい何だったのか、正確にはまだよく分からないそうだが、
たぶんガルム(garum)と呼ばれる魚醤の一種だろうというのが一般的な説のようだ。
魚醤とは、魚介類を塩漬けにして発酵させて作られる液体調味料で、
秋田のしょっつる、タイのナンプラー、ベトナムのニュクマムなどがよく知られている。
アメリカに留学していた時、同じ建物に住んでいたベトナムの学生たちが
よく夜食にベトナム料理を作ってくれたのを、懐かしく思い出す。
彼らは、ほとんど何を作るのにも、ニュクマムを使っていた。
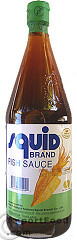 |
たしかこういう感じのものだったと思う。
においはキツイが、味は良い。
料理の腕もよかったのだろう。とても美味しかった。
古代ローマの人々にも、魚醤は好まれていたようである。
プリニウス(Plinius, 23-79AD)の『博物誌』(Naturalis historia)には
次のように記されている(31.43)。
更にひとつ、卓越した液体がある。それは人々がガルムと呼んでいるもので、
魚の内臓とその他の本来なら捨てるべき部分を塩漬けにしたものである。
ガルムとはまさに、それらが腐敗して生じる液に他ならない。
腐敗して生じる液・・・こう言われては何だか食欲が失せてしまうが、
たしかに、においは強烈だもんなあ。
しかしながら、ガルムは、非常に高価なものだったらしい。
プリニウスは続けて言う。
かつてこれは、ギリシア人たちがガロスと呼んでいた魚で作られていた。
(中略) 現在は、「同志たちのガルム」という、カルタゴ・スパルタリアの
養魚場のサバで作られたものが天下一品であるとされており、
およそ2コンギウスが、銀貨1,000枚で取引されている。
香油を除けば、他のどんな液体も、これ以上の値段がつくことはまずなく、
製造者たちの名声をも高めている。
2コンギウスは約6.4リットルである。
「同志たちのガルム」(garum sociorum)が高級品だったことについては、
マルティアーリス(Martialis, 40-104頃)の『エピグランマタ』(Epigrammata)
にも記述がある(13.102)。
<同志たちのガルム>
生きのよいサバの上等の血から作られた名高いガルムを
高価な贈り物として受け取りたまえ。
高級なガルムは、宴会客への贈り物などとしても用いられていたそうである。
アピキウスの『料理帳』の料理に、いかにも気楽に使われているリクアメンが、
そんなに高価なガルムだったとはちょっと考え難い。
おそらく、ガルムにも高いものから安いものまで色々あって、
普段は比較的安価なものが用いられていたのではないだろうか。
私自身は今のところ、日常的に魚醤を使ってはいない。
しかし、良いものを1本手に入れて食堂に常備しておき、
時々古代ローマの味覚に思いを馳せるのも悪くないな、と思った。
2007年6月の雑記へ
2007年8月の雑記へ