 ①神 |
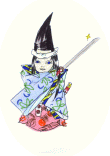 ②男 |
 ③女 |
 ④狂 |

|
能のお話
●能の演目パターン
能の演目は約250もあります。演目とは劇とほぼ同じ意味ですが、 劇の中に舞いが入ったものが演目だと考えるのが妥当でしょう。
「能」が出来た当初は次々に新しい能の話がつくられてましたが、 それらの数が多くなるにつれて話をパターン化するようになってきました。そして、そのパターンが5つに分類され、その分類は今日に至るまで残っているのです。
さて、それでは5つのパターンの特徴を見ていきましょう。
5つのパターンは主人公(シテ)の種類別に分類されます。
それらは下の5種に分けられます。
 ①神 |
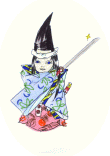 ②男 |
 ③女 |
 ④狂 |

|
この5種は、次のような呼び名が使われています。
①神⇒脇能物 ②男⇒修羅物 ③女⇒鬘物 ④狂(狂人)⇒雑能物 ⑤鬼⇒切能物 |
江戸時代までは能は1日中演じられていました。 能の演目を公演するときには上の5つの種類の物をそれぞれ1つづつ、計5つの演目を1日で上演していたのです。
そこから、毎回、1日の1番最初に演じられるものを「一番目物」、2番目に演じられる物を「二番目物」、3番目に演じられる物を「三番目物」、4番目に演じられる物を「四番目物」、5番目に演じられる物を「五番目物」と呼ぶようにもなりました。
では、この5つをそれぞれ詳しく見ていきましょう!
 |
1<脇能物>
|
演目の例:敦盛、清経、忠度、経正、屋島など
演目の例:羽衣、熊野、井筒、杜若、吉野天人など
演目の例:殺生石、猩々、土蜘蛛、紅葉狩、船弁慶など |