|
2要因分散分析 ある得点について,学年別,性別に比較したい場合(つまり,その得点に影響を与えるものが2つ(2要因)存在する場合)には,「一般線型モデル」を使います。全てののケースが以下のやり方でいけるわけではありません。いろいろな計画ごとに計算が変わってきますので,その都度やり方を調べてください。 とりあえず,シンプルな被験者間計画と,繰り返しを含んだ混合計画の場合のみ,ごく簡単に紹介します。 ●被験者間計画 以下の手順でダイアログボックスを開きます。 そうすると「1変量」というダイアログボックスがあらわれるので,「従属変数」に平均を比較したい変数を入れます。次に,群を分ける変数を「固定因子」の中にいれていきます。右に並んでいるボタンから「オプション」をクリックし,「記述統計」にチェックしてやると,各セルごとの平均値などを計算しておいてくれます。 2要因分散分析については,平均値を図示するとわかりやすくなりますよね。これは,右の「作図」ボタンから作ることができます。それをクリックすると,「1変量:プロファイルのプロット」というダイアログボックスが表示されます。 もし,以下のような図を作りたいのであれば… 「因子」から,「横軸」というボックスに,学年をあらわす変数を移動させます。そして「線の定義変数」のボックスに,性別をあらわす変数を移動させます。そして中段にある「追加」というボタンをクリックすると,その下のボックスに,例えば「学年*性」というような変数間が「*」で結ばれたものが現れます。その後で「続行」をクリックしてダイアログボックスを閉じます。 これで図示もしてくれます。 ●混合計画(反復測定) どういう計画のイメージかというと,例えば2つのクラスを対象にして,月曜日に漢字テストを行ったとします。そして1のクラスでは,その後3日間毎日漢字の宿題を与え,もう1つのクラスでは何もしなかったとします。そしてその週の金曜日に再度漢字テストを行いました… 以下の手順でダイアログボックスを開きます。 分析 そうすると「反復測定の因子の定義」というダイアログボックスがあらわれます。上部に「被験者内因子名」というボックスと,「水準数」というボックスがあるのがわかると思います。ここには,その名前にあるように被験者内の要因について入力していきます。「被験者内因子名」にはすでにfactor1と入っていると思います。特に変える必要もありませんが,例えばこれを漢字テストとしておきます。月曜と金曜という2回実施しているので,水準数には「2」と入力します。そして「追加」をクリックします。そして最後に,下の方にある「定義」をクリック。 すると次に「反復測度」というダイアログボックスが出てきます。上部に「被験者内変数」,中段に「被験者間因子」というボックスがありますが,ここに変数を移動させてやります。「被験者内変数」は漢字テストの点数なので,「月曜テスト」と「金曜テスト」の2つを動かします。「被験者間因子」には「クラス」を指定します。これで,最小限の設定は済んだので「OK」。 ここでは,本当に単純な手順のみを記しています。そのため,さまざまな事後処理を指定できる「その後の検定」の使い方については書いていません。3水準以上あるような場合の事後処理については,各自で調べてください
分析
→ 一般線型モデル
→ 一変量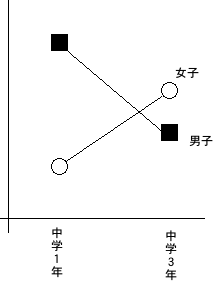
こういった時に得られたデータから,宿題の効果があったのかどうかを確認するというような計画です。なお,変数名は月曜のテストの点数を「月曜テスト」,金曜のテストの点数を「金曜テスト」,クラスは「クラス」という変数名だとします。
→ 一般線型モデル
→ 反復測定
「オプション」「作図」も,ほぼ被験者間計画の場合と同じように使えます。